葛城市の農産物のご紹介(第3回: 里芋)

ご存知ですか?
葛城市の農業生産額は県内39市町村の中で第6位、中でも野菜の生産額は県内第4位です!
| 1位 | 五條市 | 326 |
| 2位 | 天理市 | 119 |
| 3位 | 宇陀市 | 111 |
| 4位 | 葛城市 | 67 |
| 5位 | 田原本町 | 58 |
表出典: 令和5年市町村別農業産出額(単位: 1,000万円)
日々の生活を支え、葛城市にとって欠かせない産業でもある「農業」をもっと身近に――。
そんな思いから、数か月にわたり葛城市の農産品をご紹介します。第3回でご紹介するのは「里芋」です。 葛城市内で生産されている里芋について、市内の生産者さんにお話を伺いました。
なお、本インタビューは令和7年広報かつらぎ11月号にも掲載されています。
奈良県葛城市における里芋の生産

里芋の圃場
里芋は乾燥と寒さに弱い作物です。 暑くて水が手に入るところが栽培に適しています。
吉野川分水の恩恵を受けていることもあり、葛城市では里芋が広く栽培されているようです。
ただし、土用干し(止水日)で水が止まる日は焼けてしまわないように注意が必要ですね。
――中井有機園さんの里芋についても教えていただけますか?
里芋の種類としては一般的に石川早生(わせ)が多いと思います。
大野芋、土垂(どだれ)、赤目芋(あかめいも)、セレベス、八頭(やつがしら)、海老芋(えびいも)などがあるんですが、うちが作っている里芋は……何かわからないんですよ(笑)
――そうなんですか!?
はい。30年ほど前のことだと思いますが、御所の方でお薬を仕入れている方に「富山でおいしいお芋があるから」と種芋を分けてもらいました。
種類はわかりませんが、ねっとりしてモチモチして、みなさんおいしい言ってくれていますので、種類を変える気はありません。里芋は里芋ですからね。
里芋の栽培と有機農業について

掘り出された里芋
――生産で苦労されることはありますか?
里芋は手間がかかるんですよ。里芋を掘り、土を取り除き、根を取り、洗い、それを干さなければいけません。袋入れをして販売するまでが大変です。
里芋を1反も栽培していたら手で掘るわけにはいかないので芋掘機をトラクターにつけて起こして掘ります。根を取るのは毛羽取り機という機械に入れて取っていますし、芋を洗うのにも芋洗い機のような機械を使っています。
機械ばかり使いますが、そうでないと手がかかります。
それが販売価格にも反映されており、葛城市で生産された里芋は500グラムで280円や350円ほどに販売価格が設定されています。それでもおいしいので売れていますよ。

機械で里芋の根を取り除いている(動画ファイル:10.8MB)
――手作業はありますか?
掘り出した子芋をバラす(分離する)のはどうしても手作業です。掘り出してからは、田んぼで朝から夕方ごろまで半日ほど干して、切り口を乾燥した状態にしてから集めて持って帰ります。
じゃがいも等と違って、里芋の子芋は掘り出したあとで割るので断面ができます。その断面をできるだけ早く乾かさないと、傷んで腐ったりカビが生えたりしてくるんです。
里芋にはべったりと粘土質の土がついていますから、パートさんたちが丸太かた作った道具で土を取って粗割りしています。

掘り出された里芋には土がついている
――植えるのはいつ頃でしょうか?
里芋は4月ごろに植えています。マルチに穴をあけてから、芽の出てきた芋を深めに植えます。
本葉が3枚程度になったら大きな芽を1つだけ残し、他の脇芽を切り取ります。5-6月ごろに追肥をするのが一般的ですが、当園では行わず、その後は乾燥に注意しながら水の管理をして収穫時期まで育てます。
里芋は寒さにあてるとすぐ腐ってしまうので、一般的には1-2月頃になると里芋を「囲う」といって凍らない工夫をします。掘り出した芋を穴に埋めて藁をかぶせたり、土を盛ったりして、里芋が凍てつかないようにするんです。
当園でも昔は米の藁を集めて束にしていましたが、ここ数年は違ったやり方で囲っています。
夏から冬まで草刈りをせずに草を生やしておきます。その草は冬になると枯れると倒れて敷き藁代わりになるので、霜よけ対策になり3月になっても収穫ができます。
――生えてくる草とそういう風に向き合うのはとてもおもしろいですね。
とにかく手がかからずに農業をする方法はないか模索していった結果、今のやり方にたどり着きました。
他にも、省力化のために生分解マルチを貼っています。生分解なので収穫するころにはマルチがボロボロになっていて、そのまま里芋を掘ることができます。
また、伸びた草は緑肥としても活用します。細かくした草をトラクターで土の中に入れると有機物が入って土がフカフカになるんです。
たとえば耕作放棄地で草だらけになっていた田で米を作るときは、無肥料でやらないと肥料っけが多すぎて倒れてしまいます。それぐらい、草を吸い込んだ土には栄養分がどんどん蓄えられているんですよ。
当園では一つの農地で米、なす、里芋、オクラという順番で作っています。

生産者がわかるシールがついている
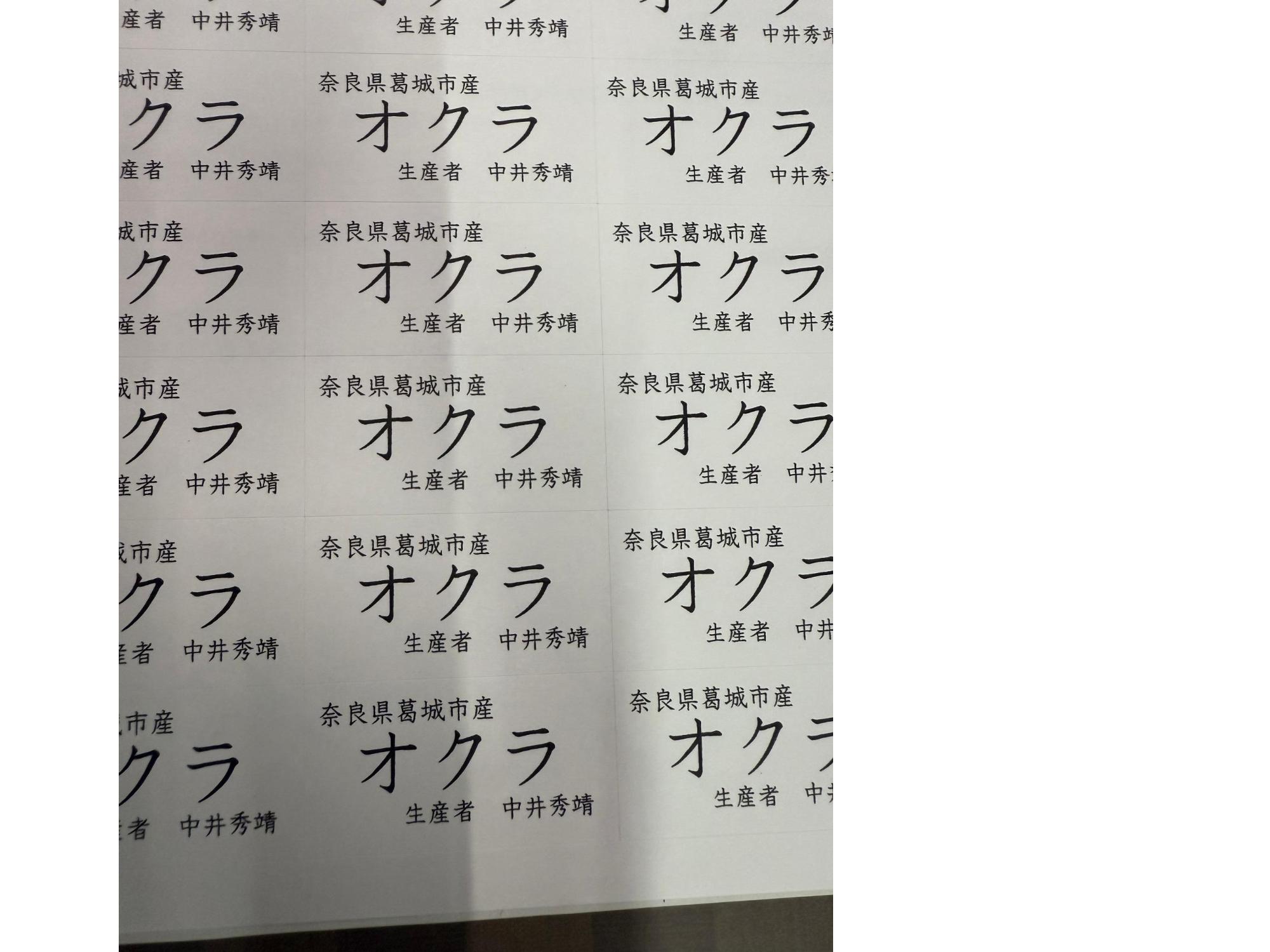
――その順番には何か意図があるのでしょうか?
田に水を入れて代かきをすると、ヨトウムシのような虫を駆除できます。また、窒素、リン酸、カリウム、カルシウム、マグネシウムといった微量要素が田の中に入り、野菜はそれらを吸って成長します。
米を作ったあとはなすを作ります。虫がいないので農薬も不要です。なすの後は里芋を作るのですが、まだ地力があるので米ぬかのような有機肥料を入れるだけで作れます。
里芋が終わると次はオクラを作ります。オクラの木は1株が大きく、次に野菜を作るのが難しいため、農地に水を入れて米を作ります。
オクラの木を片付けるのも昔は苦労したんですよ。オクラの木はとにかく乾かないので、燃やそうとしても燃えてくれません。そこで、オクラの木をチップにしてトラクターで田んぼへ返しています。オクラの木を燃やさなくても済み、田に地力がつき、片付けも早く済んでいます。
オクラは市内の給食センターにも持って行っているので、学校給食にも出ています。「今日の給食はじいのオクラやったで」と孫から言ってくれることもあります。

二上山を背景にしたオクラの木
葛城市産の里芋を買うには
――葛城市産の里芋はどこで入手できますか?
市内の道の駅(道の駅ふたかみパーク當麻(當麻の家)、道の駅かつらぎ)で入手できます。
他にも農産物直売所では葛城市産として表示されていますし、農民連に出しているものは「葛城市産」というシールを作って貼って出荷しており、東京や滋賀の生協で売られています。
また、近隣地域の各スーパーマーケットや、共同購入などでも入手できます。
――おすすめの食べ方や料理はありますか?
煮物にしたり、コロッケにしたりして食べるとおいしいです。
孫芋のような小さな芋は衣被(きぬかつぎ)といって、皮付きのまま上下の先端を切って蒸すと、つるんと皮をむいて食べられますよ。
取材協力(生産者さんについて)

農業を始めて3-4年ほど経ったころ、国から資金を借りて建てたハウスが台風で倒れてしまいました。借りた資金はハウスで得た収入で返済する必要があったので、もう一度ハウスを建てることになりました。
資金は10年で返し切りましたが、台風被害を受けるビニールハウスは減らそうと思いました。そこで旬のもの、作りやすいものを露地で作る方向へに転換していったんです。旬のものはおいしいですからね。
農業をやるにはお金がかかります。例えばお米を作るのには、トラクター、田植え機、コンバイン、乾燥機、もみすり機などが必要です。買い揃えていくと、1,000万円では買えません。

――1,000万円ですか。資金を借りて農業を始めるのは大きな決断ではありませんでしたか?
元々は金融機関やディスカウントショップで働いており、その後農業をやることになりました。子供が病気だったこともあって、健康面を重視して有機野菜に取り組みました。
葛城市内には有機野菜に取り組んでいる方がおられたので、話を聞きに行ったところ「ええなあ」と。勢いで入ってスタートしました。
結び

- 有機栽培をされている
- 事業として成立するよう効率も考えられている
自然の性質と、農業という人間の営みが、見事に調和されていると思いました。
インタビューを通じて里芋の魅力が見えてきました。そんな葛城市の里芋の魅力を少しでもお伝えできたでしょうか?
また、今後もホームページにて葛城市の農産物をご紹介します。以下のページも併せてご覧ください!













更新日:2025年11月01日